tsugái eyewear
ツガイアイウェア

【眼鏡職人 x 伝統工芸 に化学のエッセンスを】
眼鏡業界において多くの金属部品は量産を目的としたプレス加工により作成されております。それに対し私の作る眼鏡は200年、300年前から刀の鍔などに使用されていた伝統工芸の技法を用いています。 また、高分子化学の知見により、伝統工芸の技法と眼鏡製造技法を繋ぐ事を可能としました。
デザイナーの北村拓也さんは、メガネの産地である福井県鯖江市でメガネ職人として活動。その後、フランスの老舗メガネ工房Dorillat社でオーダーメイドフレームの製作を手掛け、職人として活動をつづける。2019年に帰国し、京都の伝統工芸の名工から「布目象嵌(ぬのめぞうがん)」を学ぶ。伝統工芸の技術を取り入れながら新しい表現を追求している。
フレーム価格 : ¥110,000 〜
① 金属部品
布目象嵌という技法を用いて24金を埋め込んでます。 またエイジングの表情を出すために漆に炭を混ぜ、凹凸のある表面仕上げをしてます。
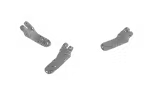
② 鋲
鋲には煮色仕上げと呼ばれる金属工芸の技法を用いています。素材には真鍮を使用しており、真鍮鋲を薬品と共に煮出すことによって、深みのある色付けをしてます。

伝統工芸技法
③テンプル芯部品
芯金には通常は洋白を使用します。この眼鏡はテンプルのバネ性、強度向上を目的として、バネ素材の鉄を使用しています。
⑤眼鏡拭き:セーム革です。奈良の鹿の皮をなめした物です。
・洗濯はぬるま湯または中性洗剤とご一緒に揉み洗いしていただき、陰干しをお願いします。 乾燥後、少しゴワっとした感じになりますが、揉んで頂くと柔らかさが戻ります。

④眼鏡ケース:桐箱に「砥の粉(とのこ)、ロウ引き仕上げ」をしています。これは、桐ダンスや、桐下駄で使われてる仕上げ方です。
よくあるパッケージとして使われてる桐箱と見比べてもらえれば、違いはすぐ分かるかと思います。
*砥の粉仕上げとは京都の山科という地域で取れる砂です。砥の粉を塗って仕上げる名称です。
*ロウ引きとはロウを塗っています。ロウを塗ることで、耐水性をあげてます。
(桐箱はとても軽いですが、柔らかい素材です。そのため傷は付
きやすいため、持ち運びは推奨しません)
tsugái eyewear取り扱い注意事項
tsugái eyewearデザイナー、北村 拓也さんインタビューhttps://www.hauskatavata.com/single-post/tsugaieyewear






















